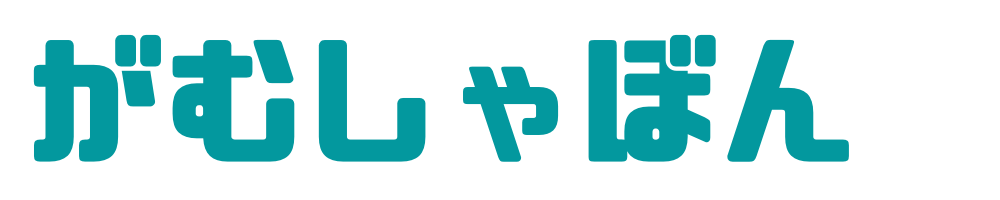最新の心理学で自制心のコントロールの仕方がわかりました!「やってのける」
我慢とか根性が自制心ではありませんでした
この本を読むと得られるもの
自制心の手に入れ方がわかります。
的確な目標の立て方がわかります。
人にモチベーションを持って動いてもらう方法がわかります。
最近特に自制心の無さを痛感しています。誘惑に連敗です。むしろ完敗です。
どうしたもんかとこの本を読んで、いろんな勘違いに気付きました。
失敗の原因って根性が足りなかったんじゃないんですね!
著者のバルパーソンさんは社会心理学者として目標達成と動機付けを研究されてきました。
人は禁煙やダイエットが続かないと「私ってなんでこんなに意志が弱いんだろ…」と嘆き、無理に努力しても無駄なんじゃと考えます。
嬉しいことに、それは無駄ではありません!
意志の力の正体は、一般的に思われているようなものではないからです。
心理学では意志の力を「自制心(セルフコントロール)」と呼びます。
自制心は目標達成には不可欠な能力であり、誘惑に打ち勝つ為にも役立つものです。
まず自制心とは、「誰かには多くあって、誰かには少ない」というものではありません。
そしてどれだけ自制心が優れていても、失敗はします。各分野で活躍する有能な人も禁煙には失敗したりするでしょ?
重要なのはやるべき事が分からず失敗するのではなく、「何をすべきか知っていながら失敗する」という人がほとんどだという事です。
常識だと思われている事が、逆に目標達成の妨げになっています。
最新の科学が常識をひっくり返す好例です。
この本では、
成し遂げるための科学
ゴールをかためる
なぜそこを目指す?
おのれを知る
楽観するか、悲観するか
ただ成功してもうれしくない
欲しいものと邪魔なもの
背中を押す
地道に壁を越える
シンプルな計画をつくる
自制心を日増しに伸ばす
現実を見よ
あきらめるとき、粘るとき
フィードバックの魔法
の項目で、目標達成についての効果的なアプローチを示してくれてます。
ここでは、どうすれば目標は達成できるのかについて簡単に要約します。
もちろん実際にはもっと奥深いものなので、是非本で確認して欲しいです。
まずは効果的な目標設定から
監督や上司が「ベストをつくせ」というアドバイス、よくありますよね。
これは残念ながら全く効果がありません。
必要なのは「具体的で難易度が高い目標」の設定です。
もちろん非現実的な目標はダメですが、「難しいが可能」という目標は自ずと最適な方法を選ぶようになります。
普段、行動を目標にする場合、「掃除をする」だと、
- 快適な住まいを作る…抽象的
- 床に掃除機をかける…具体的
となります。上記は「なぜ」、下記は「何」で動機付けしています。
これには使い分けが必要だったんです。
抽象的な思考は、小さな行動に大きな意味を結び付けれる為、意欲を高めやすくなります。
一方、具体的な思考は、難しく不慣れな行動や学習をする際に効果を発揮します。
何事であれ、最初は具体的に、楽になってくると抽象的に考えるようにします。
初めてスキーをするなら、「颯爽と滑ろう」と考えてはいけません。
膝を曲げて、スキー板の扱いに集中します。
何かを学ぶときは、最初は面倒でも繰り返し手を動かす事が効果的です。
面倒でも紙に書くようにすると、後できっと役に立ちます。
ダイエットならやる事、上手くいかなかった理由を書きます。
そしてその行動をとりたい理由を書きます。
習慣になるまで、何度もこれを繰り返して下さい。
「いつ」も必ず決めます。
研究では、決行日が近づくと気が重たくなっていく傾向がある事がわかりました。
なるわー。
人は、思いがけず訪れた近い将来の機会に対しては、なかなか積極的になれません。
得られるものよりも現実的な問題ばかりに目がいくからです。
つまり、予定を決める時は、近い将来か遠い将来のどちらについて考えているのかを自覚する必要があります。
それが自分の思考にどのような影響を与えてるのか考慮すると、よい判断がしやすくなります。
また、「何」に注目すると先延ばししにくくなるという研究結果もあります。
何をすべきかを意識する事で、具体的な行動に着手しやすくなり、目標に向かって進み出します。
逆に「なぜ」と理由ばかり考えてると、なかなか実行に移せません。
大切なのは「何」と「なぜ」のどちらかに片寄る事なく、対象の目標を達成する為にはどちらの考えを持つべきか判断する事なのです。
ポジティブに考えるけど、甘くみてはいけない
よく「あなたは必ず成功する。きっと簡単に障壁を乗り越えられる」と自己啓発とかで言われます。
でもこれは大きな間違いです。
前者のポジティブ思考は有効ですが、後者のような考え方は逆効果です。
「成功出来ると信じる」と「容易に成功出来ると信じる」では、大きな差を生み出す事が分かったのです。
成功を手にする人は、成功を確信すると同時に、成功の為には厳しい道のりを乗り越え無ければならないという覚悟をしていたのです。
ここでは、「得られるメリット」と「乗り越えなければならない障壁」の両方を考えます。
それにより目標を採用するかどうかの判断に役立ち、決めた場合のやる気を高め、それに向かって邁進しやすくなるんです。
満足をもたらす3つの要素
どんな目標でも達成すると嬉しいですよね。
その中には一瞬で消えるものもあるし、いつまでも消えない喜びもあります。
恋が始まった時、家族と過ごした時、自分の成長を感じた時、人の為に行動した時。
これらの時に私たちは真の幸せを感じます。
多くの心理学者が賛同する「自己決定理論的」では、基本的欲求には、
- 関係性
- 有能性
- 自律性
の3つであるとしています。
関係性は他者と結びつき、互いに尊重し合う関係を築きたいという欲求です。
集団に帰属する、人に会う、絆を深める、社会に貢献するなどの行為が、関係性の欲求に応えます。
有能性は、周囲への影響力を持つことや、それによって何かを得ることに関わりがあります。
スポーツ、芸術、創造性など得意な分野があることは、私たちが生きていく上でとても重要になります。
有能性の欲求は、好奇心や自発的な学びの意欲、困難の克服時に感じること自尊心を促します。
自律性は、自由に関する欲求です。
自らの行動を選び、主体的に関わることを意味します。
他者からの強制ではなく、自発的な興味から行動する動機付けを、心理学では「内発的動機付け」といいます。
これは、最も良いタイプの動機付けです。
うちの会社では、店舗に防犯用という名の監視カメラが設置されました。
カメラの映像をみた本社からあれやこれやと指示が来ます。
かなり鬱陶しくて、嫌で辞めるひとも出てきてるのですが、これはまさに自律性の不満ですね!
自発的に行動しているという感覚は、成功率も上がるそうです。
目標を自ら選ぶことで、内発的動機付けが生じます。
それにより、楽しさ、好奇心、創造性、理解などが高まります。
「やってのける」を読んでやってみた
目標の使い分けが素晴らしい
実践してみた3つのこと
- 状況に合わせて目標を変えてみた
- 選ぶ要素を入れるとよいとわかった
- 報酬を使うのは気をつけるべきとわかった
状況に合わせて目標を変えてみた
目標説的だけでも相当な情報量でした。
上記にもあるけど、使い分けが大切なんです。
でも、なんか難しいですよね。
ざっくりとまとめていきます。
詳しくは本で確認して下さいね!
簡単なことや、得意なことをする時は、能力を示すの目標と、得られるものに注目する目標を設定します。
やる気がない時は、「なぜ」に注目して目の前の行動を大きな目標の一部と捉えると良いです。
さらに失敗すると失うものをイメージするとブーストかかります。
難しいことに挑戦してする時は、目標をを具体的に設定します。
習得型の目標を持てば、失敗を繰り返しながらも成長していくのに役立ちます。
誘惑に負けそうな時は、「なぜ」の思考で目標の本来の姿を思い浮かべます。
失うものをイメージするのも誘惑に負けにくくなります。
スピードが必要な時は、得られるものにフォーカスした目標が最適。
創造性を求められる時は、獲得できるものを目標にします。
自律性の感覚は創造性を高めます。
選ぶ要素を入れるとよいとわかった
計算問題が順番に出てくるソフトを使った研究があったのですが、面白い結果だったんです。
このゲームでは、学習内容を選択することは出来ません。
ただし、一部の生徒には学習と無関係の部分を選択できるようにしたんです。
自分のアイコンと選べて、登場する宇宙船に名前を付けれるようにしました。
実験の結果、アイコンを選んだりできた生徒の方がゲームを楽しみ、休み時間もし続けたりしたんです。
選択の感覚を与えるだけで、自律性の要求が満たされて、内発的動機付けが高まり、大きな成果を生んだのです。
これすごい面白いですよね。色んなことに応用できる。
他人に目標を持たせる時に使えますね。
報酬を使うのは気をつけるべきとわかった
3歳から5歳の子供にマーカーを渡して、絵を描く遊びをやってみる実験がありました。
一部の子供には、「上手に絵が描けたらご褒美をあげる」と伝えます。
すると、ご褒美について聞かされた子供は他の子供より多くの時間マーカーを使って遊びました。
数週間後、興味深い結果になったのです。前回ご褒美をもらった子供は、ご褒美がないと全くマーカーに興味を持たなくなったのです。
ご褒美を貰うことで内発的動機が無くなったんですね。
しかし、全ての報酬が動機付けを無くすわけでもないそうです。
事前に知らされず、予定外に与えられたご褒美はあまり悪影響がありません。
褒め言葉でも興味を失うことはありません。
つまり動機付けで報酬を与える時には、内発的動機付けをよく理解して使うことが大切なんですね。
これ、経営者が知らんかったらかなりやばいんちゃう?
内発的動機は脅威、監視、時間的制約などでも低下するそうです。
これは面白いですねえ。
いかがですか、今回も長文になってしまいました。
最初の頃の文章の2倍にもなってます。まあ自分が面白かったらそれでいいですね。
この本もかなり面白かったです。
関連記事 この投稿も読んでみよう!
人の褒め方、モチベーションの高め方など様々な心理学が学べます。
著書名 やってのける
著者 ハイディ・グラント・ハルバーソン
出版社 大和書房