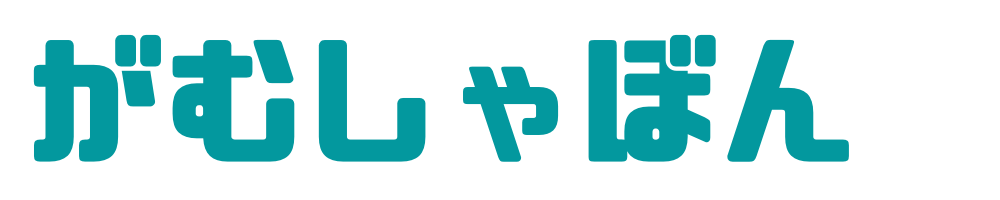この本を読むと得られるもの
- お寿司についての知識が増えて、より美味しく頂けます。
- お寿司の技術がわかります。
寿司の楽しみ方、職人技「寿司のこころ」
みんな大好きお寿司ですが、意外とみんな知らないことを書いてみた
世界でも大人気のSUSHI。
先日は堀江さんと寿司職人の本を紹介しましたが、寿司の世界の奥深さに触れ、色々寿司関係の本を読んでおります。
ここでの寿司とは一般的に「にぎり寿司」と呼ばれてれるものです。
日本の寿司の歴史は、大陸から伝わってきたといわれており、朝廷への貢物にされていました。
飛鳥時代には「養老令」の中でも「鮑の鮓」「雑魚の鮨」という言葉が出てきます。
奈良の平城京跡では「多比(鯛)の鮓」という木簡も出土しています。
この時代のお寿司は保管に優れた「なれずし」です。
乳酸により菌の繁殖を抑えるだけではなく、旨味成分も出て美味しさも増しています。
にぎり寿司の誕生は江戸時代になります。
「早すし(一夜すし)」の登場です。
諸説ありますが、両国にあった「與兵衛すし」の華屋與兵衛(はなやよへい)が江戸前握りすしの元祖と言われています。
この時代は芝居や浮世絵などの文化が花開き、人々が集まり食べ物屋も多く登場しました。
この時代のファストフードとしてにぎり寿司が人気になります。
この時代は一口サイズではなく、おにぎりくらいの大きさでした。
当時は冷凍技術もないので、塩や酢、醤油に漬けたり、煮たりといった工夫がされていました。
やがて氷が手に入りやすくなり、生の魚をすし飯に乗せた現代に近いにぎり寿司が登場しました。
また冷蔵により遠方から魚が取り寄せれるようになって、にぎりの種類も一気に増えました。
魚の味を楽しんでもらおうと、すし飯の量がここで変わりはじめます。
おにぎりの大きさから、10個20個と食べれるスタイルになります。すし飯も魚を活かすように淡白になりました。
どうです?面白いですよね。
ここまではこの本の記載ではないのですが、いやないんかい、寿司の知識が増えたので披露しました。
この本では、
日本が誇る寿司の求道者10人
寿司屋の楽しみ方
寿司の基礎知識
さらに広がる寿司の世界
の項目で書かれています。
このブログでは、「寿司の基礎知識」の項目を要約します。
本はフルカラーでめちゃめちゃ美味しそうです。
是非本で眺めてくださいね。
お寿司の材料基礎知識
お米
まずはお米。
現在日本に登録されているお米の品種は約6000種類です。
その中から、寿司屋に人気があるのは「ササニシキ」「コシヒカリ」「ハツシモ」です。
日常食卓で食べられる品種とはちょっと違いますね。
寿司屋の好みで共通してるのは、粘りっけが少なく、崩れにくいしっかり硬いお米です。
米粒の大きさは1.8〜1.9cm程度。この微妙な差に寿司屋は気を配っています。
お米は熟成米が使われます。
9月ごろに収穫し、それから3ヶ月は「新米」と呼ばれます。大体の人はこの新米を狙っていますよね。
熟成米とは低温倉庫で1年以上熟成させたものを言います。
中には2〜3年熟成させたものを使うお店もあるんですって。
熟成米は炊く時にお水を十分に吸わせないといけません。ここが寿司屋の腕の見せ所です。
海苔
巻き寿司に使われる「海苔」も違うんでしょうか?
もちろん違います。家庭用の焼き海苔では塩気が強く、酢飯の味を邪魔するので使えません。
また、塩分が多いと水分を吸うと縮むので、巻き寿司には弱くなります。
寿司屋が理想とする寿司海苔は強い香り、歯切れが良い、口溶けも良い柔らかさを兼ね備えています。
特に有明海の海苔が人気で使われています。
酢
一般的に白・淡い赤・濃い赤の3種類の酢を使い分けて握ります。
寿司といえばネタばかりが注目されますが、酢飯なしではお寿司になりません。
できるだけネタを美味しくする為に酢飯ももちろん使い分けます。
白身魚には白酢が合います。赤酢だと強い香りが主張しすぎて白身との相性はイマイチな感じです。
ヅケの鮪などは逆に存在感のある濃い赤酢でないと負けてしまいます。
組み合わせで美味しさも変わっていくんですね。
酢飯はご飯が炊き上がったら、すし桶の中で酢を満遍なくかけます。
しゃもじで飯を底から大きく返して、切るように混ぜていきます。
うちわであおいで粗熱を取り、酢飯にツヤを出します。
炊き上がってからわずか10分の早業です。
醤油
寿司のクライマックスを決める醤油も大切。
寿司屋が使うのは「煮切り醤油」と呼ばれるものです。
「煮切る」とは、酒やみりんを煮てアルコール分を飛ばすことです。
醤油とともに調味料や出汁を加えて煮切ることで、塩分を抑えた寿司を引き立てる醤油が出来ます。
もちろんブレンドは各店が試行錯誤した上で見つけたオリジナルです。
昆布や醤油のブレンドも使われます。
醤油はたまり醤油や再仕込み醤油などいろんな作り方があります。
関東では赤く透き通った濃口醤油が好まれ、関西では濃いたまり醤油が好まれています。
「寿司のこころ」を読んでやってみた
知らないと楽しめないことも多い
今入院してまして、病院のベッドの上で「お寿司食べたいなあ」と思いながら書いております。
「俺、退院したら、お寿司食べにいくんだ…!」
といそいそとフラグ立ても忙しいです。
同じ食べるものでも、知識として知っているかいないかは美味しさに直結すると思います。
なんかの漫画でも「奴らはラーメンを食っているんじゃない。情報を食ってるんだ」というセリフがありました。
創業者のストーリーや材料の希少性は美味しさを後押ししますよね。
お寿司も職人さんの技を見抜けると、普通に口に入れてる人より感動しながら噛み締めると思います。
まさに情報を食べているわけです。
関連記事 この投稿も読んでみよう!
お寿司についてもっと知りたい!ってなったので読みました。
著者
出版社 エイ出版社