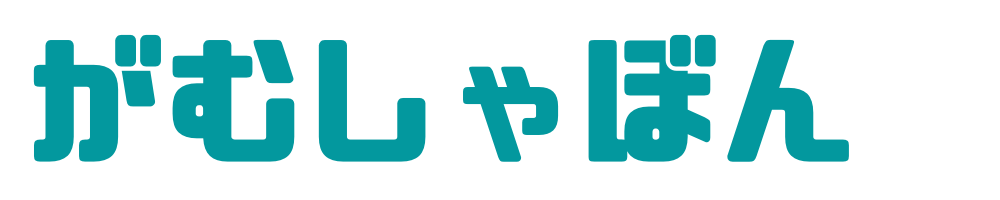この本を読むと得られるもの
- 売れる接客のポイントがわかります
- 商品のストーリー作りが学べます
- 売り場の作り方がわかります
「売れる店頭は何が違うのか?」思わず買ってしまう販売の極意!ひと工夫だけで売上は何十倍!
商品の魅力をいかに演出するかが腕の見せ所
モノもお店も溢れるこの時代、どれだけ品質が良くてもそれだけではモノは売れません。
逆に知名度はなくても売れる商品もあります。
なぜそんなことが起きるのでしょうか?
著者の久野さんは販売促進の仕事の中で、試行錯誤を繰り返しながら様々な方法を実践検証されてきたのです。
するとある時から「消費者心理」がわかるようになってきたそうです。
その結果、POPだけで売上が何倍にもなったり、2時間のお試し販売で商品が完売したりするようになったんです。
そこからホームページや広告手法にも応用されるようになりました。
一気にご自身の会社経営も加速したのです。
まさに「モノを売る原点は店頭にあり!店頭を制するモノは全てを制す!」です。
この本では、
- 『ステージ』9回裏ツーアウトぁらの逆転劇へようこそ
- 『企画プロデュース』アピールではなく、パフォーマンスで売れ!
- 『舞台演出』なぜあの店頭には人だかりができるのか?
- 『販売』同じ売り方でもこれだけ違う。売れる販売促進術
- 『ファン作り』売れる店舗には必ず感動がある
という項目で、消費者心理、販促、売れるPOPなどについて解説されてます。
小売業はもちろん、様々は商売で活用できると思います。
この本を読んで是非愛される店舗の礎を築きましょう。
売り場でメッセージを伝えよう
店頭は思考が一瞬で切り替わるステージです。
その直前まで買う気がなかったものを買ってしまうことってありますよね。
他のものを買おうと思ってたのに、店頭で実物を見て、POPなどの新たな情報でそれらが消えてしまうこともあります。
逆に店頭での販促がずさんだと、広告などそれまでの努力が全て無駄になります。
こういった点でも、中小メーカーは店頭という場をおざなりにしてはいけません。
もはやモノやサービスだけで差別化を目指すのは難しくなってきました。
ネットでモノが買える以上、安さで勝負するのも限界がきています。
ここからはアイデア勝負なのです。
世の中で人気のあるもの、売れているものは全て共通点があります。
それは「お客様を追う立場ではなく、追われる立場にある」ということです。
そう言われると、そうですよね。
この発想を抜きに優位な立場で経営をすることは出来ません。
追う立場である「対応型」の経営だと、アピールや売り込み、媚びたり安売りしたり、他社との比較や競争にさらされます。
その結果、価格競争や長時間労働となりストレスもハンパないです。
逆に追われる立場である「創造型」は、パフォーマンスや演出、価値の創造、共感や感動を生み出します。
それはまさにストレスなく販売でき、従業員のモチベも上がり、健全な経営が営める状態です。
お客様目線で見ても、普段は商品アピールばっかりで、媚びて安売りするような相手には魅力を感じません。
他にもっと安いところがあればそっちに行きます。
しかし魅力的なパフォーマンス表現を展開しているところにはワクワク感を感じ、お店や商品の応援する気持ちまで芽生えます。
価格に左右されることなく、購入し続けます。
最初の発想が違うだけで、大きな差を生み出すのです。
久野さんがとある高級ウインナーを販売していた時。
一袋1280円のウインナーはどれだけ説明したり、試食してもらっても最終的には隣の300円のウインナーが売れる状況でした。
まさに心が折れる中での販売…。
そんな時、ある年配の女性が説明もそこそこに4袋も買っていったのです。
驚いた久野さん。なぜそんなに買ってくれるのか尋ねたところ、旦那さんがめずらしく「美味しい」と言ってくれるからだそうです。
ここがまさに「消費者心理」がわかった瞬間です。
お客様は美味しいウインナーが欲しいのではない。
旦那さんに「美味しい」と言ってもらいたい。
その体験を得るために1280円を払っているのです。品質とは別に大きな価値があるわけです。
そこで久野さんは早速POPを書いてみました。
『無口なお父さんが「美味しい」と言ってくれます』
「今春、関東の食品展示会で消費者人気No. 1になったこだわりの本格ハムです。
食べ応えのある大きさなので、2〜3本でメインのおかずになります。
これからの季節、お鍋に入れても最高です。」
すると、徐々にポップの前に人だかりができてきました。
娘さんが面白がって「ねえ、お母さん。見て、これ買って帰ったらいいんじゃない?」とお母さんを呼んできてくれました。
色んな人が商品を手にとって見てくれたり、POPを見て試食したいと言ってくれたりと、全く状況が変わったのです。
それまで週に4袋しか売れなかった商品が、一日で500袋売れる結果となったのです。
商品を購入した後に何が待っているのか?
何が得られるのか?
これを「見える化」したことで、お客様を追う立場から、追われる立場に大逆転したのですね。
お客様の心の奥にある欲求を掘り起こし、言葉としてポップで明確化する。
その結果、感動や共感を呼び、それが購買のスイッチになります。
先ほどの例だと「喜んでもらいたい」という部分が刺激されたわけですね。
そうなると価格の壁も難なく乗り越えることができます。
顕在的欲求を刺激するのは、安さや便利さ、美しさなどです。
潜在的欲求を刺激するのは、得られること、悩みからの開放などです。
潜在的欲求が刺激されると「そうそう!」って感じで、改めて自分の中の欲求に気付きます。
これこそ追う側から追われる側へと変わる瞬間なのです。
「売れる店頭は何が違うのか?」を読んでやってみた
売れる売り場ってこだわりの塊
実践してみたこと
- 売り場を演出しよう
五感の中で、人間が物事を判断する割合は、視覚が83%、聴覚が11%、嗅覚3.5%、味覚1%だそうです。
視覚って重要なんですね。
商品の陳列もただ並べるだけでなく、積み方や配列、色合い、角度などを考える必要があります。
さらに売れるお店では視覚だけでなく、それ以外の五感に訴える訴求が数多く仕掛けられてます。
例えば、人の声には「声紋」といわれるものがあります。
聞き手はその声紋によって受ける印象も随分変わるそうです。
心地よく感じる声、感情がたかぶる声、納得してしまう声。
これらは訓練である程度コントロールできるそうです。
声のトレーニングやりたいなあ。
1万人に1人の割合で「1/fゆらぎ」という特質の声を持つ人が存在するそうです。
これは生まれ持ったものらしく、聞き手はこれを感知すると、自律神経が整えられて精神が安定したり、活力が湧いて興奮したりするんです。
ジョン・レノンや美空ひばりさん、宇多田ヒカルさん、森本レオさんや花澤香菜さんなどの声がこれにあたるそうです。
ゆらぎは無理でも、落ち着いた話し方は意識したいです。
BGMも奥が深くて、ピアノ曲は人の声に近い波長なので、隣接した席の会話が聞こえにくくなるそうです。
ジャズやボサノバは、滞留時間を長くする効果があるんですって。
店をするならBGMにはジャズを導入するといいですね。
BGMの選曲で、店の印象を操作したり、客層を選別したりも出来ます。
僕もBGMプレイリストを作ります。
また、匂いも大切な要素です。
飲食店はもちろん離れたところから購買欲求を高めるのに効果ばつぐんです。
お店だとアロマの香りでお客さんの緊張感を和らげて、滞留時間を伸ばすことが出来ますね。
ローランドさんがオススメしてた香水でも置こうかな。
実店舗の魅力は
- 商品に直接触れることができる感動
- 空間が演出する興奮や刺激
- 人との出会いやふれあい
この3つが強力なものです。
1は、繁華的刺激、臨場感、催事やイベントです。
2は、五感で感じる、吟味できる、比較できるなどがあたります。
3は、人との交流、影響力、欲求解消などがあります。
ここを極める為にも、「場」の雰囲気作りは大切です。
ガッツリ作り込みます!
とりあえずこの本を読んでやってみよう、な!
関連記事 この投稿も読んでみよう!
小さいお店の戦い方。競ってはいけません。
著書名 売れる店頭は何が違うのか? 思わず買ってしまう!集客販売の極意
著者 久野和人
出版社