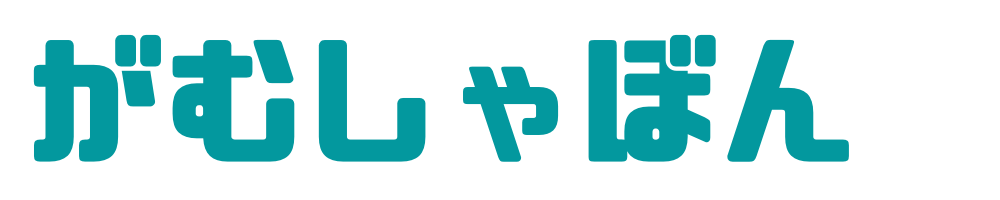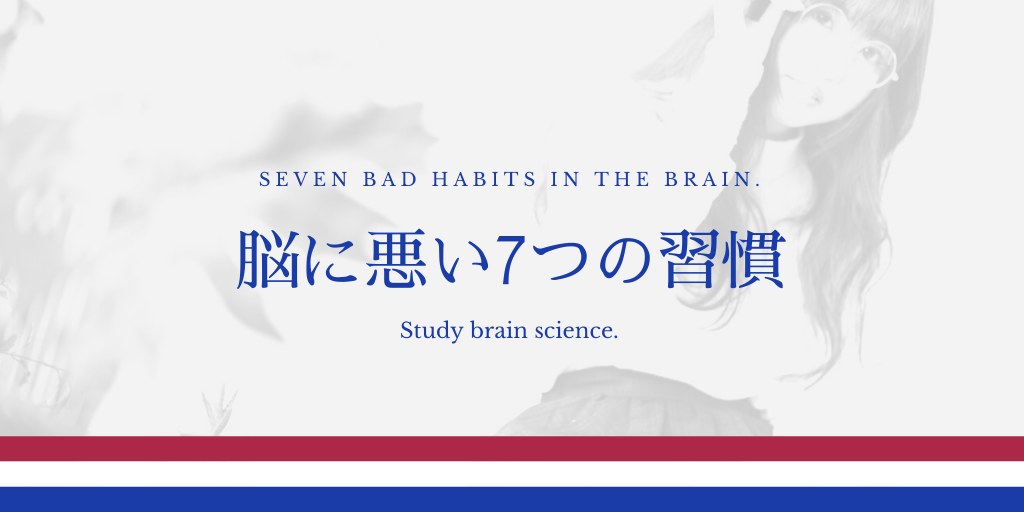
「脳に悪い7つの習慣」をやめれば、記憶力も思考力も爆上がりです
脳の仕組みから「脳に悪い習慣」がわかる
この本を読むと得られるもの
脳に悪い習慣を理解して、改善することができます。
改善できると脳がよく働いて、パフォーマンスが上がります。
「嫌い」の感情を理解できて、人間関係も改善できます。
著者の林さんは脳神経外科医として、長年に渡って脳の研究をされてきました。
同時に「脳をフルに働かせる」ことも課し、その方法を模索されてきました。
脳に悪いことをやめていけば、物事への理解力は高まり、ここぞという時に最高のパフォーマンスを発揮し、独創的な思考が出来る様になります。
集中力を高め、記憶力を良くすることも可能です。
脳科学バンザイ!
脳の仕組みから理解しておきましょう。
目から入った情報は、「大脳皮質神経細胞」が認識して、「A10神経群と呼ばれる部分に到達します。
「A10神経群」は、
- 危機感を司る「扁桃核」
- 好き嫌いを司る「側坐核」
- 言語や表情を司る「尾状核」
- 意欲や自律神経を司る「視床下部」
などが集まった部分です。ここで生まれるのが「感情」です。
脳では情報に対して最初に「好き」「嫌い」という気持ちが発生するわけです。
そして「A10神経群」は情報に対して感情のレッテルを貼ります。
レッテルを貼られた情報は、次に「前頭前野」に入ります。ここでは情報を「理解・判断」します。
自分にとってプラスの情報あると、その情報は「自己報酬神経群」に持ち込まれます。
さらに自分にとって価値あるものにする為に「線状態-基底核-視床」「海馬回・リンビック」に持っていくのです。。
このような流れを作りながら、脳は考える機能を生み出すのです。
ここまででも脳をダメにする習慣がなんとなくわかりますよね。
入ってきた情報に「嫌い」のレッテルを貼ると、理解や思考、記憶の過程で、レッテルに引っ張られてうまく働かなくなるのです。
逆な好きなことには、頭がよく働いて、いいパフォーマンスを上げられるのもわかります。
この本では、脳の仕組みに従って「脳に悪い習慣」と「その習慣をやめ、脳を活かす為の具体的な方法」が書かれています。
この本を読んで実践して、パフォーマンスを上げていきましょう!
脳に悪い習慣たち
脳に悪い習慣は全部で7つあります。
- 「興味がない」と物事を避ける事が多い
- 「嫌だ」「疲れた」とグチを言う
- 言われたことをコツコツやる
- 常に効率を考えている
- やりたくないのに、我慢して勉強する
- スポーツや絵などに興味がない
- めったに人を褒めない
なんか3とか4とか「え?やってるけど…」って思う人も多いはず。
「興味がない」と物事を避けるのはダメ
脳は本能に逆らえない
脳が最初に情報を受け取る脳神経細胞は、生まれながらにしてその一つ一つが本能を持っています。
それはたったの3つです。
「生きたい、知りたい、仲間になりたい」
人間の脳が何を求めて機能しているかを知っておくのは重要です。
そして明確なのは、脳の機能。最大限に活かすには、本能を磨くべきだという事です。
「自分さえ良ければ」は思ってはいけない
脳には本来、「仲間になりたい」という本能があるので、他人が喜ぶのは嬉しいものです。
他人と関わらず生きていく事は出来ません。
この本能を現代社会の枠組みの中に置けば、脳が求めるのは、「世の中に貢献しながら、安定して生きる」ことなのです。
「貢献心」は二次的な本能で、これを磨き高めることは脳の力を発揮するベースになります。
ここは脳の自己報酬神経の機能とも密接に関わります。
「興味が無い」と考えるのもダメ
脳の思考や記憶に大きく関わるのが「知りたい」という本能です。
これは脳の原点とも言えます。
赤ちゃんの脳が情報の伝道路を形成するのにきっかけになるのが、お母さんへの「興味」です。
人間にとって「興味を持つこと」こそが、すべの始まりです。
幼少期には興味を持たせることを大切にして、脳の構造が定まる4歳までは物事に興味を持つ事を教えましょう。
幼児に対しては「ダメ」「やめなさい」という否定語は使ってはいけません。
物事への興味が薄い人は注意が必要です。
脳の考える仕組みが機能しなくなり、脳の神経伝達路も衰えていくからです。
「知りたい」という脳の本能を磨くには「興味が無い」と考えたり、口にしないことです。
人の話を聞いたり、本を読んだりする時に「そんな事知ってる」と思うのも、興味がないのと同じです。
脳の発達に関わる2つのクセ
もう一つ、脳の仕組みで知っておかなくてはならないものがあります。
神経細胞が集まって脳組織を構成し、好きとか理解するなどの機能を生み出しますが、この機能を守る為に第2段階の本能が生まれます。
それが「自己保存」と「統一・一貫性」です。
前者は「脳は自分を守ろうとする」、後者は「脳は統一性、一貫性が保てなくなるような情報を避けようとする」ということです。
もちろんプラスの作用も待っていますが、反面で脳が間違いを犯したり、脳のパフォーマンスを落としたりする原因にもなります。
わかりやすいのが、人は自分と反対の意見を言う人を嫌いになるという反応です。
冷静に考えれば、意見が違っても嫌いになる理由はないはずです。
しかし、脳は異なるものを「統一・一貫性」に外れる為拒絶し、「自己保存」が働くことで自分を守ろうとする為、相手の意見を論破しようとさえします。
不祥事を起こした人が更に悪事を重ねる様子を見て、不思議に思う時がありますよね。
素直に謝って原因を追及した方が復活の道が見えるのに、大企業のトップでさえよくわからん自らを追い込む言動を見せたりします。
これも「自分の立場を捨てたくない」という「自己保存」のクセが過剰に働いているのです。
「自己保存」の過剰反応は身を滅ぼします。大切なのは、自分の脳にもこのクセがあることを自覚して、それに引っ張られないように注意しましょう。
「嫌だ」「疲れた」とグチってはいけない
マイナスの感情は持つな
脳は情報にレッテルを貼ると書きました。
つまり、人間の脳が理解したり、思考したりして記憶する情報は、すべて感情のレッテルがついたものなのです。
これが何を意味するのでしょう?
理解力、思考力、記憶力。この高めたい能力たちは、どれも最初の「感情」によってパフォーマンスが左右されます。
一度マイナスのレッテルを貼られた情報は、記憶も思考もされにくくなるのです。
試験勉強や仕事に取り組む時、トレーニングする時でも、最初から「面白くない」「好きじゃない」と思ってませんか?
一度A10神経群で「嫌い」が貼られると、脳はその情報に対して積極的に働かなくなります。
脳の理解力や記憶力を高めるには、まず「面白い!」や「好き!」というレッテルを貼らなければなりません。
「でも苦手なものは、そうそう好きになれないし…」
確かにそれありますよね。でも、ここで大切なのは苦手なものを嫌がるのではなく、まずは興味を意識して持ってチャレンジしてみる事です。
様々なものにチャレンジし続けることは、興味と関心を司る「側坐核」を鍛えます。
でも「チャレンジしたけど、やっぱり苦手やわ」って時はどうすればいいのでしょう?
そんな時は「この条件において」という前提を置いてみる事が有効です。
「この状況下では自分が最強だ」と考えてみましょう。範囲を狭めた中でやってみるのです。
「嫌だ」「疲れた」を口に出すのはNG
「疲れた」が口ぐせの人がいます。「愚痴を言った方がストレス発散になる」と勘違いしてる奴もいます。
ところが、こうした否定的な言葉は、自分が言っても、周囲が言うのを聞いても、脳にとっては悪影響しかありません。
何気なく口にしても脳はマイナスのレッテルを貼ります。
しかも愚痴から何か新しい発想が生まれる事もまずあり得ません。
ここは意識して強い気持ちで「グチは絶対に言わない」と心に決めましょう。
感動しないと脳は鈍る
感動と言っても、号泣してみたいな大袈裟なものではありません。
日常生活の中でも人の話を聞いた時や、新しい知識に触れた時に「あ、それすごいな」と思う程度でも大切なのです。
これはA10神経群に感動を司る「尾状核」があり、気持ちを動かすと判断力と理解力が高まるからです。
「感動する力」は脳をレベルアップさせます。
誰かが話す時には「すごいね」「面白いね」と意識して言葉を添えながら聞きましょう。
表情が暗いと脳も曇ります。「尾状核」は表情も司っており、表情筋とも繋がっています。
意識して目や口の表情筋を刺激して、努力してでもニカーッと笑顔を作りましょう。
顔の筋肉はA10神経群と密接に関連しているからです。
「脳に悪い7つの習慣」を読んでやってみた
言われたことをコツコツやらない
これ結構気になってたんですよね。
なぜ「言われた事をコツコツやる」のは脳にとって悪いのでしょう?
「言われた事をコツコツやる人」ってむしろ褒められてる印象ですよね。
しかし脳の達成率を上げ、集中してことを成し遂げるには間違いなんですって。
スポーツとかで勝負所で全力投球が必要なのはもちろんです。
この全力投球とコツコツは全くの別物です。
目標は高く設定する事が大切なのです。
あまり高い目標だと脳が「自己保存」に走って「無理だ」という気持ちが生まれてしまうので、大体130%ぐらいを目指して目標を立ててスタートしましょう。
自己報酬神経群は、「自分からやる」という主体性を持って、考えたり行動したりしないと機能しません。
上司や先生に言われたからという意識だと、物事が理解出来ても、思考が働かないのです。
「言われた事をコツコツやろう」ではなく「自分がやるからにはもっと良くしてやろう」と「自分から」というスタンスが重要です。
これは意識的にやらないと、なかなか出来ないですよね。
指導する時も、あれやれこれやれではなく、自己報酬神経群の働きを理解した指示を出さないと、能力を引き出す事も出来んなあ。
特に失敗した時に「こうすれば良かったのに」と責める言葉もダメです。
「自己保存」が強くなって「言われた通りにしよう」とばかり考えるようになるよね。
「どうしたらいい?」と意見を持たせる言い方が大切なんですね。
気をつけようっと。
脳科学って難しいけど、理解すると強力な武器になりますよね。
是非残りの「やったはいけない事」も本でチェックして下さいね。
関連記事 この投稿も読もう!
自分自身の可能性も縮める「バイアス」も取っ払いましょう!
著者 林 成之
出版社 幻冬舎