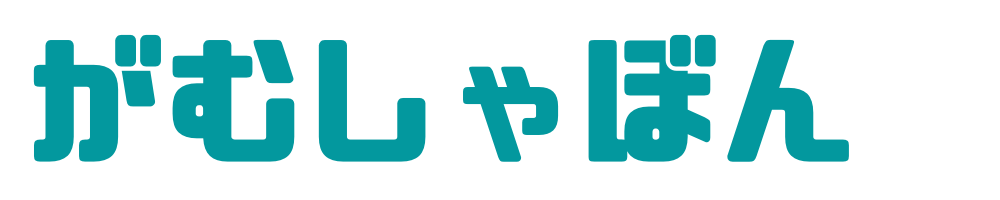堀江貴文「グルメ多動力」でこれからの飲食店業界の変化を知ろう
無人化店舗とかどんな感じになるんやろ?
この本を読むと得られるもの
これからの飲食店がどのように変化していくのかわかります。
高級店の楽しみ方がわかります。
無人化の流れについて理解出来ます。
堀江さんは365日外食をしています。
「WAGYUMAFIA」という和牛を広める活動もされてます。
そんな中で、外食業界にも接点の多い堀江さん。
業界は目まぐるしいスピードで変化しているそうです。
SNSやグルメサイト、コンビニの台頭などなど。
以前は鮨屋の本も紹介しました。
修行はいらないという発言も反響が大きかったですね。
この本では、
「ドタキャン」「食べログ」「人材の確保」問題の現在
Instagram全盛期、SNSの波に乗るのは常識に
飲食を取り巻くモノ、ヒト、コト
無人コンビニのイートインで飲むのがスタンダードになる
最も大事なのはコミュニケーション能力である
今ある店を進化させる、進化した店を出す
最近行って「なるほど」と思ったお店
堀江貴文×光山英明
堀江貴文×「鮨人」木村泉美
「予約の取れない料理屋」の予約を手に入れるとっておきの方法
などの項目で書かれています。
ここでは、「無人コンビニのイートインで飲むのがスタンダードになる」の項目を要約していきます。
他の気になる項目は是非本で読んでくださいね。
コンビニで飲むのがスタンダードになる
コンビニご飯ってどんどん美味しくなってますよね。
コンビニご飯は体に悪いとも思われてますが、健康を意識したものも増えています。
特においしいのが冷凍食品です。
セブンイレブンはかなり力を持って入れていますよね。
コンビニには以前からイートインがありますが、今後はもっと広くなると予想されてます。
激安居酒屋で飲むよりも、コンビニで計算し尽くすされた秒数です温められた冷凍食品と、缶ビールを飲んだ方がよっぽど美味しいからです。
大阪地下鉄が売店なコンビニを採用したところ、歳入は5倍になったそうです。
それぐらい支持されているんですね。
極端な話で言えば、コンビニの横に場所貸しの三沢つくったっていいくらいです。
こちらも無人で出来るし、可能性はあります。
ビジネスホテルもしょぼいレストランを併設するくらいなら、コンビニをつくればいいくらいです。
ホテルに大浴場を作ると水道光熱費が大幅な節約できたように、コンビニへ宿泊客を誘導する事で、レストラン運営のインフラコストを下げつつ、満足度を上げる事も出来るでしょう。
コンビニももはや店員がいる必要もなくなりました。
ひとりで会計して、チンして、のんびりした方がよっぽどいいです。
アマゾンも「Amazon Go」という無人コンビニのシステムを開発し話題になりました。
3月には、この「Just Walk Out」(ジャスト・ウォーク・アウト)と店舗技術を販売すると発表しています。
こうなれば、誰でもライセンス料を払えばこのシステムを使う事が出来ます。そうなるとあっという間に広がるでしょう。
無人コンビニの利点は店舗側にもたくさんあります。
やる気のないバイトを雇わなくていいだけではありません。
コンビニが抱える最大の問題は、利益率がとても良い低い事です。
最初は儲かりましたが、今ではかなり厳しいです。
無人になると、万引きが大変なんじゃ?と思いがちですよね。
無人コンビニの先駆けである中国では、ほとんど発生していないそうです。
中国ではアリババやWeChatが運営する「信用システム」というものがあります。
連携しているコンビニで負債を働くと、個人のスコアが大きく低下します。
すると決済サービスが使えなくなるなど、ペナルティが発生する為、みんな真面目にスコアを上げる努力をしているのです。
Amazon Goだとコンビニのもうひとつの大きな問題、廃棄も解決できます。
コンビニでは未だにバイトが年齢や性別のボタンを押す事でデータを集めています。
これが画像認識でほぼ正確にわかるようになりました。
仕入れもお店の商品状況が把握できるので、ここでも人の手は無くなるでしょう。
近い将来、必ずコンビニは無人化します。
そこから無人居酒屋に無人カフェなど、色々発展していくでしょう。
おそらく牛丼屋なども厨房が自動化され、無人を目指すようになります。
チェーン飲食店におけるリスクは従業員が生み出しているので、この流れは止まらないと思います。
勝間さんがやってる「ロジカルクッキング」がスタンダードになるかもですよ。
ITや技術系ではオープンソースは一般的です。
この波は飲食業界にもやってきそうです。
今までは長年修行しないと教えてもらえなかった技術やアイデアが、ネットで簡単に知ることが出来ます。
レシピ動画を見れば、簡単に同じものが作れるようになりました。
アイデア自体の価値はどんどん低くなってます。
これからは自ら発信していく事で世界にも飛び出せるのです。
「お店を持つ」というリスクも回避できる!
世界一のレストランと言われる「ノーマ」は、常時お店を開いているのではなく、定期的にポップアップレストランを開くというスタイルです。
堀江さんのWAGYUMAFIAも基本はイベントとポップアップです。
飲食店の廃業率は18.9%と大変厳しい状況です。
でも、やり方次第では「店舗を持つ」リスクは軽減されます。
今はシェアリングサービスが充実しているので、他の店の空いている時間を使わせてもらう事も出来ます。
持ち主も使わない時間をお金に換える事が出来ますよね。
僕の家の近くにも、昼間は粉物屋で夜はバルというお店があります。
以前紹介した「佰食屋」さんも参考になりますよね。
長時間営業に頼るのではなく、効率化でキチンと利益を出されてます。
従業員も飲食店につきまとう長時間労働から解放されて、休日もきっちり家族と過ごすことができるんです。
コロナ後は、テイクアウトに特化するお店も増えました。
これだとお店も必要なくて、集客の多い場所です販売出来ます。
家賃の安い地方でオープンするのも増えてきました。
地方で出店するのも昔よりやりやすくなりました。辺境の地でもお客さんは来るようになりましたよね。
情報さえきっちり発信すれば、どこでも人はやって来ます。
むしろ、辺境の珍しい立地の方がお客さんも喜びますよね。
地方だと仕入れも安く済みますし、珍しい食材が話題にもなります。
日本のレストランはとてもレベルが高いので、海外でも十分に戦えます。
「グルメ多動力」を読んでやってみた
お店の紹介を再開しよう
これから人気の出る飲食店は、無人化と高級店化の二極化が進みそうな話でしたね。
僕はこのブログ以外にも、奈良の「ならまち」を案内するブログもやってます。
コロナの自粛期間の間、更新が止まってしまいましたが、そろそろ再開してもいいかなって感じです。
奈良の街全体にも活気が少しずつ戻ってきています。
再開は趣向も変えて、リニューアルスタートにしようと思ってます。
手書き地図を加えていこうかな。
それを集めて編集すれば、書籍化も狙えそうですしね。ウシシ。
対談も面白かったです。
ぜひ読んでみて下さいね。
関連記事 この投稿も読んでみよう!
無人化に興味がある方は、こちらもチェックしてみてね。
著書名
著者
出版社